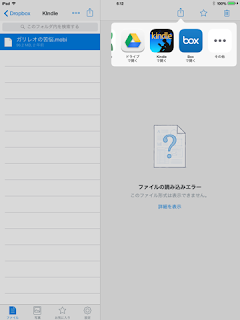早朝に出社し夜の残業を減らす「朝型勤務」が企業の間に広がりをみせている。仕事を効率化させ、社員の私生活の充実や、残業代など経費の削減につなげるのが狙いだ。政府も6月にまとめた新しい成長戦略で、仕事と生活の調和を取るために朝型勤務の普及をうたっている。ただ、同じ企業内でも部署ごとに仕事内容が違うため、一律の義務づけは難しそうだ。日本総合研究所の村上芽めぐむさんは「(主に社内で仕事が完結する)総務系などの部門では実施しやすいが、社外とのやり取りが多い部門は朝型に抵抗を感じるだろう」と指摘する。
取り組んでいる企業としては伊藤忠、八木通商、オプトといったところが取り上げられているのだが、「うーむ」と思うのは、朝型勤務が、いわゆる「残業代削減」という文脈で語られているところ。これは、政府の改訂成長戦略でも同様で、「働きすぎ防止のための取組強化」という文脈なので、フレキシブルなワークスタイルの模索と言うより、経営効率のよい「働かせ方」という臭いがして、このあたり好意的でない話もちらほらみかける。
J-CAST ウオッチ "政府主導の朝型勤務 「大きなお世話」"
個人的にいうと、「一律に朝型勤務」というのは単純に労働時間をシフトさせるだけの話だから、時間外短縮の効果ではどうかな、という気がするし、少数の取組なら穴場効果もあるが社会全体が「朝型」になるということは保育所から通勤とか結局、今の状態の時間繰上げになるだけでは、と思う次第。
望むらくは、働き方の自由化というか、フレックスや在宅勤務、ノマド勤務を含め、全体としての勤務環境の緩さの実現手法と、きちんとした勤怠管理、実績管理、貢献度管理(よく実績だけで仕事の成績を評価しようという話が短絡的にでるが集団的組織で仕事をする場合、組織貢献度的な側面も考えないとささくれた職場になってかえって組織全体の成績が落ちる気がしている)の手法の確立がまず全体として必要なのではないかと思う。
一頃のように「ノマド」が一番効率良く生産的な働き方といった論説は、生産現場や研究現場を含めた労働現場全体を見ていない話であったと同様に、今回、「朝型勤務礼賛」もそれがすべての解のようになってくると、これまた全体を見ていない、全体最適を考えない話のように思える。
まあ、あまり一つの方向ばかりに偏らず、、これはこれ、それはそれ、あれはあれ、と複眼的にやったほうがよいのでありましょうな。
望むらくは、働き方の自由化というか、フレックスや在宅勤務、ノマド勤務を含め、全体としての勤務環境の緩さの実現手法と、きちんとした勤怠管理、実績管理、貢献度管理(よく実績だけで仕事の成績を評価しようという話が短絡的にでるが集団的組織で仕事をする場合、組織貢献度的な側面も考えないとささくれた職場になってかえって組織全体の成績が落ちる気がしている)の手法の確立がまず全体として必要なのではないかと思う。
一頃のように「ノマド」が一番効率良く生産的な働き方といった論説は、生産現場や研究現場を含めた労働現場全体を見ていない話であったと同様に、今回、「朝型勤務礼賛」もそれがすべての解のようになってくると、これまた全体を見ていない、全体最適を考えない話のように思える。
まあ、あまり一つの方向ばかりに偏らず、、これはこれ、それはそれ、あれはあれ、と複眼的にやったほうがよいのでありましょうな。